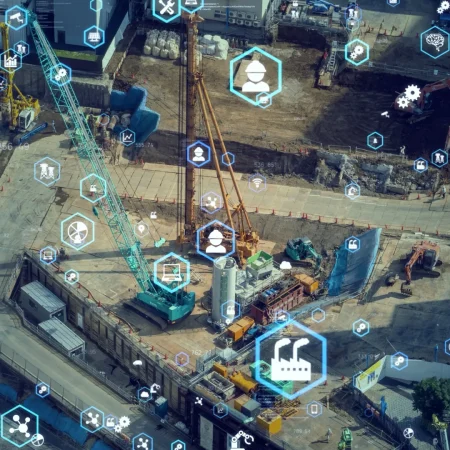SPECIAL
特集
運送業で活かせるカーボンニュートラル事例集

各業界でカーボンニュートラル(CO₂排出の実質ゼロ)を目指す動きが世界中で加速している中、特に運送業界は物流の要として多くのエネルギーを消費し、CO₂排出量も多いため、カーボンニュートラルの実現において重要な役割を担っています。本記事では、日本の運送業者が進めるカーボンニュートラル実現に向けた取組について、具体的な事例をEcoNiPassチームが紹介します。
運送業におけるカーボンニュートラル実現に向けた取組事例
大手運送業者は電動化や再生可能エネルギーの活用など、多様な取り組みを通じて環境負荷の軽減に挑んでいます。
ヤマト運輸のカーボンニュートラルへの取り組み
ヤマト運輸は、「2050年カーボンニュートラル実現」を目指し、環境負荷の低減に向けた多様な取り組みを進めています。特に、物流業界において大きなCO₂排出源となっている輸配送部門において、革新的な施策を展開しています。
まず、電気自動車(EV)の導入が挙げられます。ヤマト運輸は、2030年までに約23,500台のEVを導入する計画を立てており、2022年度には既に331台を導入しています。これにより、ガソリン車やディーゼル車に比べてCO₂排出量を大幅に削減しています。また、効率的な運行体制を構築するため、各拠点にEV専用の充電設備を設置し、充電インフラの整備を進めています。
次に、太陽光発電設備の設置による再生可能エネルギーの活用を推進しています。全国の810拠点に太陽光発電設備を設置する計画を進めており、これにより自社の消費エネルギーを賄うだけでなく、余剰電力を地域に供給することで、地域全体のCO₂削減にも貢献しています。
また、エコドライブの推進と環境教育にも注力しています。社員一人ひとりの環境意識を高めるために、定期的な研修やワークショップを実施し、燃費の改善や走行効率の向上を図っています。
佐川急便のカーボンニュートラルへの取り組み
佐川急便は、「SGホールディングスグループ カーボンニュートラル宣言」を掲げ、2050年までにCO₂排出量の実質ゼロを目指しています。物流業界において多くのエネルギーを消費する輸配送部門を中心に、環境負荷の低減に向けたさまざまな取り組みを進めています。
まず、環境対応車の導入に力を入れています。佐川急便は、CNG(天然ガス)トラック、ハイブリッドトラック、電気自動車(EV)など、低炭素型の車両を積極的に導入しており、従来の内燃機関車に比べてCO₂排出量を大幅に削減しています。また、今後は水素燃料電池車(FCEV)の導入も検討しており、次世代のエネルギー活用を視野に入れた取り組みを推進しています。
次に、モーダルシフトの推進が挙げられます。長距離輸送において、CO₂排出量の少ない鉄道輸送や船舶輸送に切り替えることで、効率的な物流を実現しています。特に、北海道や九州などの遠距離間輸送では、列車やフェリーを活用することで、大幅なCO₂削減効果を上げています。また、他社との共同配送を実施し、輸送効率を高めつつ、走行距離の短縮を図っています。
さらに、環境マネジメントの強化にも取り組んでいます。佐川急便は、ISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得しており、エネルギー使用状況を可視化し、データに基づいた効率的な運行計画を策定しています。また、社員向けの環境教育を実施し、エコドライブの推進を図ることで、日常業務におけるCO₂削減を徹底しています。
日本通運株式会社のカーボンニュートラルへの取り組み
日本通運株式会社(NIPPON EXPRESS)は、物流業界最大手として「2050年カーボンニュートラル実現」を目指し、グループ全体でのCO₂排出削減に取り組んでいます。特に、輸配送部門と物流施設における環境負荷の低減を重視し、さまざまな施策を進めています。
まず、次世代燃料の活用に力を入れています。日本通運は、バイオ燃料や水素燃料など、CO₂排出を抑える次世代燃料の利用を推進しています。特に、バイオ燃料を既存のディーゼルトラックに使用することで、車両を新たに購入することなくCO₂削減を実現しています。また、水素燃料電池車(FCEV)の導入も進めており、水素ステーションの整備にも積極的に関与しています。
次に、スマート物流システムの導入が挙げられます。日本通運は、IoT技術を活用して輸送ルートの最適化を図り、走行距離の短縮とアイドリング時間の削減を実現しています。これにより、燃料消費を抑え、CO₂排出量を削減しています。また、物流施設においては、自動化設備の導入や省エネ型の照明・空調システムを採用し、エネルギー使用量の削減を進めています。
さらに、再生可能エネルギーの活用も推進しています。国内外の物流拠点に太陽光発電設備を設置し、クリーンエネルギーの自家消費を促進しています。余剰電力は地域の電力網に供給することで、地域全体のCO₂削減にも貢献しています。
社員教育の徹底にも力を入れており、環境意識の向上を図るための研修プログラムやエコドライブの推進を行っています。これにより、現場レベルでの燃費改善やエネルギー効率の向上を実現しています。
鈴与株式会社のカーボンニュートラルへの取り組み
鈴与株式会社は、持続可能な社会の実現に向けて、カーボンニュートラルを推進する多岐にわたる取り組みを展開しています。
まず、物流の効率化を通じてCO₂排出量の削減に努めています。具体的には、CO₂排出量シミュレーションシステムを導入し、発地、着地、貨物重量を入力することで、さまざまな輸送モードにおけるCO₂排出量を簡単にシミュレーションできる仕組みを提供しています。また、フェリー輸送の活用や荷姿エンジニアリングを通じて、輸送効率を最大化し、CO₂排出量とコストの削減を実現しています。
さらに同社は、SDGs達成に向けた物流最適化サービスを提供しています。具体的には、最適な物流拠点立地の提案やシステム・機械の導入による高効率・高品質な物流構築を行い、CO₂排出量削減や労働力不足対策、BCP(事業継続計画)への対応を進めています。
これらの取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に向けて積極的に貢献しています。
西濃運輸株式会社のカーボンニュートラルへの取り組み
西濃運輸株式会社は、持続可能な社会の実現に向け、積極的にカーボンニュートラルの取り組みを進めています。特に、物流におけるCO₂排出量の削減を目的とし、モーダルシフトや次世代エネルギーの活用、輸送効率の向上を図っています。
まず、同社はモーダルシフトの推進に力を入れています。従来のトラック輸送に加え、鉄道や船舶を活用することで、CO₂排出量の大幅な削減を実現しています。具体的には、鉄道コンテナを利用した「カンガルーライナー」や、国内各地の港を活用した海上輸送を展開し、長距離輸送における環境負荷を低減しています。
また、車両の電動化にも取り組んでいます。2023年には、アサヒグループホールディングスやヤマト運輸などと協力し、水素燃料電池(FCEV)大型トラックの実証実験を開始。これにより、CO₂を排出しない輸送システムの構築を目指しています。
さらに、ダブル連結トラックを導入し、輸送効率の向上を図っています。1台で2台分の荷物を運べるため、燃料消費とCO₂排出量の削減につながっています。関東と関西を結ぶ幹線輸送では、日本通運やヤマト運輸と協力し、共同運行を行うことでさらなる効率化を実現しています。
西濃運輸は、業界全体と連携しながら、環境負荷の低減に向けたさまざまな取り組みを進めています。今後も、技術革新を活用しながら、より持続可能な物流の実現に向けた挑戦を続けていくでしょう。
日本トラック協会のカーボンニュートラルへの取り組み
運送業界全体でカーボンニュートラルへの取り組みが進められる中、公益社団法人全日本トラック協会(JTA)は、2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、トラック運送業界全体での環境対策を推進しています。その一環として、「トラック運送業界の環境ビジョン2030」を策定し、2030年までにCO₂排出量削減に向けた具体的な行動を示しました。
このビジョンのもと、JTAはエコドライブの推進、輸送効率の向上、モーダルシフトの促進など、幅広い施策を展開しています。特に、トラックの大型化やトレーラー化、再配達の削減などにより、輸送の効率化を図りながら環境負荷を低減する取り組みを進めています。また、発荷主・着荷主・消費者との連携を強化し、業界全体でのCO₂削減を目指しています。
さらに、JTAは次世代環境対応車の導入促進にも力を入れています。電気トラックや燃料電池トラック、高効率天然ガストラックの普及を支援し、持続可能な物流システムの構築を目指しています。
これらの取り組みを通じて、トラック運送業界全体が環境負荷の低減に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献しています。
運送業者によるカーボンニュートラルへの取り組みは、単なる環境対策に留まらず、企業の競争力強化やブランド価値の向上にもつながっています。また、政府や自治体との連携、他業種との協力体制を構築することで、より大規模なCO₂削減が可能となっています。今後は、さらに多様なエネルギー源の活用やAIを駆使した物流効率化が進むことで、カーボンニュートラルの実現に向けた道筋が一層明確になると期待されます。
運送業界の未来へ:カーボンニュートラル実現に向けた展望と第一歩
本記事では、運送業におけるカーボンニュートラルの具体的な事例や未来の展望について解説しました。
運送業界におけるカーボンニュートラルへの取り組みは幅広く展開され、持続可能な社会の実現に向けて大きな前進を遂げています。
今後の展望として、さらなる技術革新が重要な鍵を握ります。電気自動車(EV)や水素燃料電池車(FCEV)の普及拡大に加え、AIやIoTを活用したスマート物流の導入が進むことで、物流効率が飛躍的に向上することが期待されます。また、政府の補助制度やカーボンクレジットの活用により、経済的な負担を軽減しながら脱炭素化を推進することが可能となるでしょう。
運送業界全体が協力し、多様なアプローチを組み合わせることで、カーボンニュートラルの実現はさらに加速していきます。企業の取り組みが社会全体に好影響をもたらし、持続可能な未来へとつながることが期待されます。
本記事で紹介した事例や情報を活用し、貴社もカーボンニュートラルへの第一歩を踏み出してみませんか?CO2排出量可視化プラットフォーム「EcoNiPass(エコニパス)」はCO₂排出量のリアルタイム可視化、サプライチェーン全体の脱炭素化支援、そしてカーボンクレジットの効率的な管理を可能にすることで、貴社のカーボンニュートラルへの取り組みを支援します。