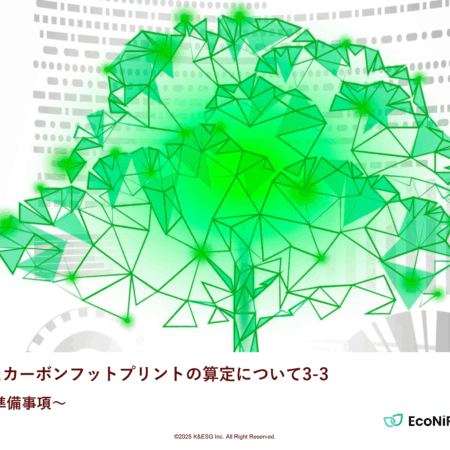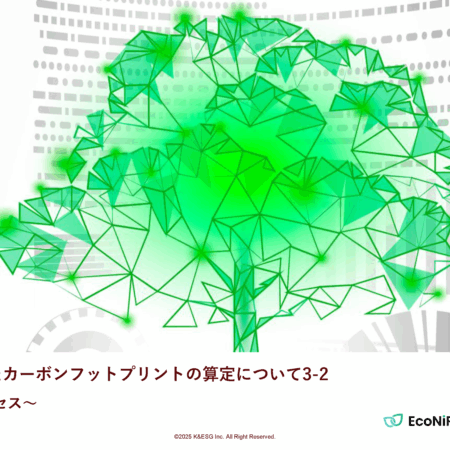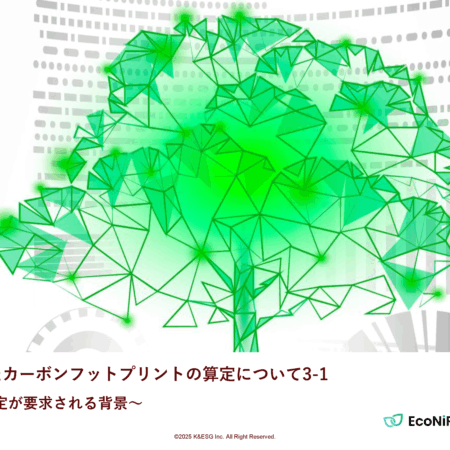SPECIAL
特集
【導入事例】多数の建設現場のCO2排出量を収集するには、現場に負荷のかからない仕組みが必要

株式会社橋本店は、宮城県を地盤とする150年近くの歴史を有する地域ゼネコンです。同社では、CSR(企業の社会的責任)の一環として環境対策にも力を注ぎ、カーボンニュートラルに関しても本格的な取り組みを開始しました。常時40程度ある建設現場でのCO2排出量を把握のために、現場の従業員や下請けの協力業者、本社の集計担当者に負荷をかけさせたくないとの思いで採用したのが「EcoNiPass」です。CO2排出量の見える化を定着させた橋本店では、環境省「エコファースト認定」の取得を目指すとともに、CO2排出量削減に向けてさらなる取り組みを進めています。「EcoNiPass」の導入・定着をリードした常務取締役 労務安全部長の村山 英明 様に話を伺いました。
導入背景
橋本店では、就業時間を早めて自動車での通勤時間を短縮することでCO2削減につなげるなど、これまでもカーボンニュートラルに向けた取り組みを進めてきました。その効果に手応えを感じた同社では、経営陣の後押しもあって、建設現場においてもカーボンニュートラルに取り組むことを決断。建設現場や下請けの協力企業、本社の担当者に負荷をかけずにCO2排出量を把握するための方法を模索していました。
課題 | ・約40の建設現場(事業所)では多種多様な重機が使用されており、データを収集するのが難しい ・現場社員や協力企業によるデータ収集、それをまとめる本社担当者のデータ入力を、負担をかけることなく行いたかった |
| 解決策 (導入ポイント) | ・レシートや請求書などに記載されている燃料使用量でCO2排出量を算出できるEcoNiPassを採用 ・データ収集は、クラウド上の共有フォルダにPDFファイルを保存するだけで完了 ・集計作業には「入力代行サービス」を利用し、本社に専任担当者を置く必要がない ・工事終了後の閲覧は課金されない建設業に適した料金体系 |
| 効果 | ・CO2排出量把握のための基盤ができ、Scope1、Scope2における排出量削減の具体策検討や、Scope3の一部実現にも道筋がついた ・環境省「エコファースト認定」の取得を目指す ・現場の若手責任者を中心にカーボンニュートラルの意識が高まる |
CO2排出量を把握する際のデータ収集・集計で苦労
橋本店は、明治11年の創業以来、宮城県を地盤として土木・建設事業を展開してきました。また、CSR・環境保全にも力を注いでおり、1万5000本の桜の苗木の植樹を目指す「橋本店SAKURAプロジェクト140」や、社員による定期的な清掃活動である「スマイルサポーター活動」などで、地域社会に貢献しています。
当社が、カーボンニュートラルを意識したのは、2024年春のことです。建設業の時間外労働の上限規制を契機に、社員や協力企業の方々の通勤時間短縮を目指し就業時間を早めることにしました。自動車通勤の者がほとんどなので、通勤時間が短縮できればCO2排出量も削減できます。アンケートをとって短縮できた時間を集計し、それをアイドリングストップの際の削減量などを参考にして数値化することにしたのです。試算では、年間62トンのCO2を削減できるということでした。
しかし、実際に行うと課題もわかってきました。データの収集・集計の作業がとても煩雑だということです。すぐにアンケート回答してくれる人もいますが、業務が多忙で回答が遅れる人も少なくありません。また、集計作業を担当する社員もかなり時間がかかり負担がかかっていました。
とはいえ、CO2削減量が数値として見える化できたことは、CO2削減の活動を本格化させて広げていく契機となりました。SDGsや脱炭素が世の中の大きな流れになっていることも感じていましたし、当社の佐々木宏明代表取締役会長CEOが「ぜひ進めよう」と積極的だったことが大きかったです。

写真:株式会社橋本店 常務取締役 労務安全部長 村山 英明 様
燃料の種類・量を入れればCO2排出量を算出できる「EcoNiPass」
ただ、それぞれの建設現場のデータをどうやって収集するのかが難題でした。橋本店では常に40程度の建設現場が稼働しており、山の土砂を削っている現場もあれば、街中でビルを建てている現場もあり、業務が一様ではありません。各現場で稼働している重機の種類、サイズもさまざまなので、CO2排出量を算出するのが難しいのです。また、データ収集の方法が各現場の負担になるようでは、協力を得られませんし、長続きもしません。「簡単で分かりやすく、続けやすいツール」にすることが重要だと感じていました。
こうして思案しているとき、社内で紹介されたのがウイングアーク1st の「EcoNiPass」です。すぐにEcoNiPassのWebサイトを確認したところ、この仕組みなら当社がやりたいことを実現できそうだと直感し、翌週の役員会議でEcoNiPassの紹介動画を見てもらいました。役員からも高評価で、ほぼ即決で採用を決めました。
EcoNiPassに決めた最大のポイントは、CO2排出量を算出するときの仕組みです。ガソリン、軽油といった燃料の請求書やレシートに記載されている数量さえわかれば、CO2排出量を算出できます。
例えば、現場で記載する日報に、使用する重機などの台数と稼働時間を記録し、そこからCO2を算出するといったシステムもあるようですが、重機が8時間フル稼働ということはありませんし、こまめに時間を記録しておくのも現場の負担になるため、現実的ではありません。
その点、EcoNiPassであれば、ガソリン・軽油といった消費した燃料の種類・量さえわかれば、EcoNiPassがCO2排出量を算出してくれます。各現場では、レシートや請求書など、燃料の種類・量がわかるものをPDFファイルにして「共有フォルダ」にアップロードするだけの作業なので、日常業務の大きな妨げにもなりません。
この共有フォルダを使ったデータ収集の仕組みはウイングアーク1stから提案を受けたものですが、もしこの仕組みがなければ、本社の担当者が各現場や300社ほどある協力企業のすべてに連絡を取りデータを集めなければならず、たいへんな労力になったはずです。
「入力代行サービス」で集計作業の負担を軽減、建設業に適した課金体系も魅力
もう一つ、ウイングアーク1stから提案を受けたのが「入力代行サービス」です。これは、各現場が共有フォルダにアップロードしたファイルをEcoNiPassに入力するのを、ウイングアーク1stが手配する企業が代行してくれるサービスです。別途費用はかかるものの、本社の担当者が入力作業をする負担がなくなり本来業務に専念できることを考えれば、コストに見合うものだと考えて採用しました。
さらに、EcoNiPassの課金体系も建設業に適したものでした。データは現場ごとに保存・集計されますが、竣工するとその現場での業務は終了します。このとき、その現場のデータは保存・閲覧可能なままですが、EcoNiPass のIDは新しい現場でも使えるため、新たにIDを追加する櫃はありません。現場(事業所)が一定ではなく、新たな現場が発生する建設業に適した課金体系だと思います。

環境省の「エコファースト認定」の取得を目指すとともに、地域の企業に脱炭素経営を呼びかけたい
当社がEcoNiPassを2024年12月に利用し始めてから数ヶ月が過ぎました。現在はCO2排出量を把握する段階にありますが、さまざまなことがデータで確認できました。当社の排出するCO2の約7割は工事現場で使っている燃料で、そのうち55%は重機が使用する軽油だったということ。ビルの建築現場よりも、基礎工事で使う大型重機を使う土木の現場の方がCO2排出量の多いといったことです。また、冬期の工事ではコンクリートが固まるまでの間、凍結を防ぐための給熱養生を行うためのヒーターによるCO2排出量も把握できました。
EcoNiPass によって、Scope1、Scope2におけるCO2排出量の把握・削減のための体制が整いました。Scope3でのセメント・生コン・鋼材といった主要資材もCO2排出量算定の対象にできそうだという道筋も見えてきました。また、現場の若手の所長から、ひび割れを自己修復しコンクリートを長寿命化させる自己治癒コンクリートや、竹を骨組みに使う竹筋コンクリートなどを使ってはどうか、といった意見が出てくるなど、カーボンニュートラルへの意識が高まっているのも感じています。
さらに、環境省の「エコファースト認定」を取得しようという目標も掲げ、2030年や2050年という区切りまでにCO2を何パーセント削減していくのか具体的な目標を策定し、それを実行へと進めていく計画です。地方を拠点とする建設会社でカーボンニュートラルを考えている企業はそう多くはないと思いますが、橋本店が先鞭をつけることで、同規模の同業企業や地元企業の刺激になればと思っています。
正直なところ、カーボンニュートラルに本格的に取り組もうと考えたとき、CO2排出量の計算は面倒くさそうで、やり方も複雑そうなので、脱酸素に対する知識のない我々建設会社の社員では簡単にはできないだろうという思いでした。ウイングアーク1stには、何から手をつけてよいのかわからないところから相談をして、それに対して丁寧に説明してもらい、我々の要望にも応えてもらえて、満足度は高いです。これからも、さまざまな面で手助けやアドバイスをいただきたいと思っています。
Company Profile

株式会社 橋本店
創業:明治11(1878)年4月20日
所在地:宮城県仙台市
URL:https://www.hashimototen.co.jp/
株式会社 橋本店
常務取締役 労務安全部長
村山 英明 様