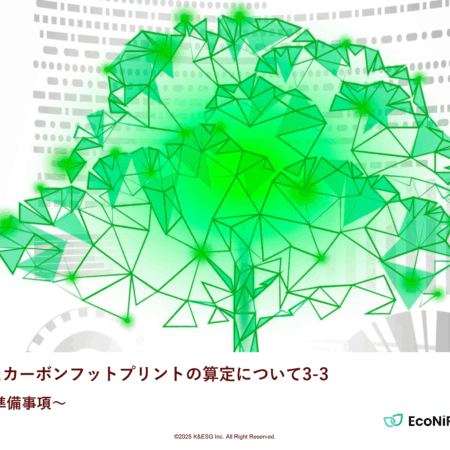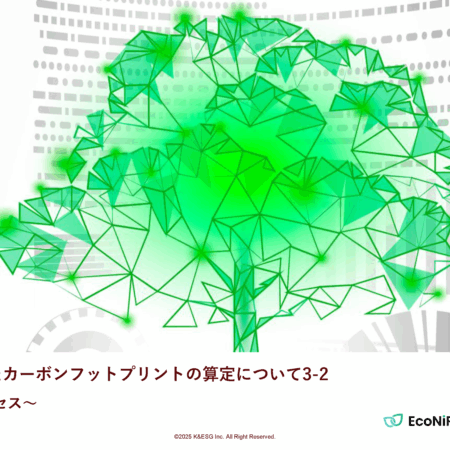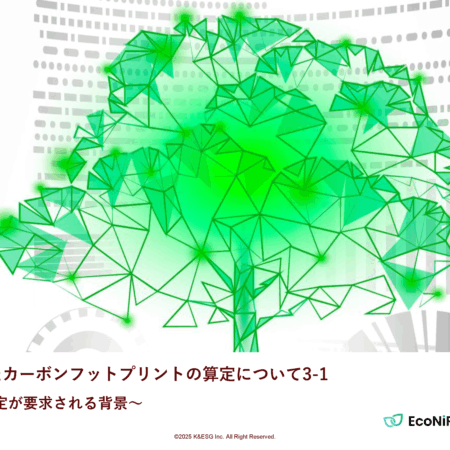SPECIAL
特集
CFP算定の業務プロセス
こんにちは、ESG職人の野底です。前回の資料でCFPを出さなきゃいけないのはわかった。でも「実際どう算定するのか」となると、途端に難しく感じませんか?私も最初は同じでした。対象製品を決めて、境界を引いて、データを集めて…と、8つのステップに分ければ道筋は見えてきます。けれど現場では「どの範囲を切り取るか」「サプライヤーからデータをどうもらうか」で悩みが尽きません。このコラムでは、私が実務でつまずきながら学んだ算定プロセスを、できるだけ分かりやすく整理してお伝えします。一緒に壁を越えていきましょう。
▶︎資料(CFP算定の業務プロセス)のダウンロードはこちら
■今回は「CFP算定の業務プロセス」の1章立てです。少しスライド数は多いですが、これを読み切れば、CFP算定の流れが理解できますよ。

■CFP算定は8つのステップに分けて進めましょう。算定の道筋を一緒に見ていきましょう。

■何のために算定するのか、利用用途をはっきりさせることが第一歩です。シンプルですが、重要です。

■業界ごとに定められたルール(PCR)は要チェックです。基準をそろえることが肝心です。

■どの商品を対象にするのか、そして機能単位をどう定義するかを決めていきます。

■製品の機能に基づいて単位を設定することが、フェアな比較への土台になります。

■製品サイズや仕様の差を乗り越えるために、機能に基づいた宣言単位が必要です

▶︎資料(CFP算定の業務プロセス)のダウンロードはこちら
著者紹介

K&ESG株式会社
代表取締役社長
ESG職人
野底 琢(のそこ たく)
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社で、業務・ITに関するコンサルティングサービスを経て、2021年にゼロボード社の立ち上げに参画。2024年にK&ESG株式会社を立ち上げ、LCAコンサルティング業務に従事
業務の傍らで横浜国立大学大学院環境情報学府に入学し、LCA環境評価手法を学習・研究。
環境情報学を背景に、ゼロボード社では事業開発担当兼コンサルタントとして、経産省・環境省による”CFPガイドライン”の実証事業のマネジメント、DADC・ABtCと連携したOuranos Ecosystemのアプリ要件(CFP算定・連携)の開発事業のリーダーを担当。その後、K&ESG社では、欧州電池規則におけるCFP・DD対応支援やCBAM対応に関するコンサルティングサービスを展開。CFPの算定経験は50商品以上に渡る(内、自動車・自動車部品関連は20商品)
また、TCFDレポート作成、CDP回答といったサステナビリティ情報開示の支援経験は60社超に上る