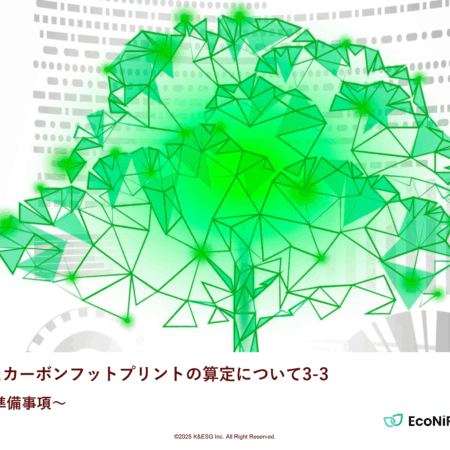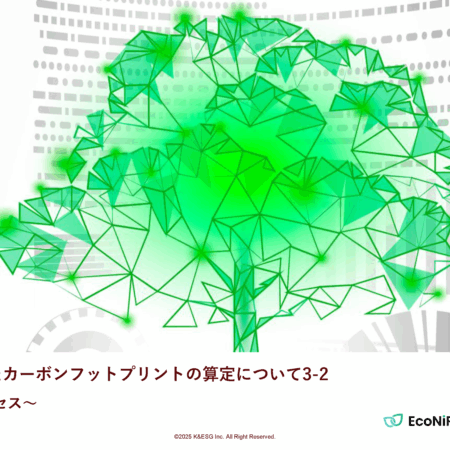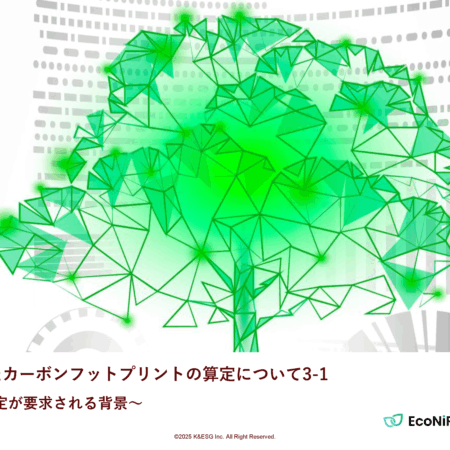SPECIAL
特集
CFPの概要とCFP算定が要求される背景
こんにちは、ESG職人の野底です。この数年、CFPの開示をめぐる空気がガラリと変わりました。欧州では電池やアパレルで「出さなければ販売禁止」の規制が始まり、日本でもOEMや業界団体からの要請が次々と押し寄せています。現場では「なぜ今そこまで?」と戸惑う声も多い。でも、背景を知れば腹落ちする部分もあります。エシカル消費の広がり、サプライチェーン全体での脱炭素、国の動き。私は実務で何度も企業と一緒に悩みました。このコラムでは、その背景を現場目線で一緒に整理してみたいと思います。
▶︎資料全文(CFPの概要とCFP算定が要求される背景)のダウンロードはこちら
■本資料は、「CFPの概要」と「CFP算定が要求される背景」の二つの省に分かれます

■まずはCFPのコンセプトを一緒に押さえましょう!

■次に、その排出量をどう算定するのか ― 活動量に排出係数を掛け算するシンプルな仕組みを、現場感覚で見ていきましょう

■算定に欠かせない『排出原単位』、実は研究データを積み重ねてつくられた信頼のものさしなんです。

■簡易的に算定の全体像をイメージで確認しましょう、素材から廃棄までどんな活動が数字に変わるのかを一緒に見ていきましょう。

■ちょっとややこしくなります。CFPの兄貴分であるLCAもここでおさえておきましょう

■科学的かつ歴史のある取り組みなんですよ

▶︎資料全文(CFPの概要とCFP算定が要求される背景)のダウンロードはこちら
著者紹介

K&ESG株式会社
代表取締役社長
ESG職人
野底 琢(のそこ たく)
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社で、業務・ITに関するコンサルティングサービスを経て、2021年にゼロボード社の立ち上げに参画。2024年にK&ESG株式会社を立ち上げ、LCAコンサルティング業務に従事
業務の傍らで横浜国立大学大学院環境情報学府に入学し、LCA環境評価手法を学習・研究。
環境情報学を背景に、ゼロボード社では事業開発担当兼コンサルタントとして、経産省・環境省による”CFPガイドライン”の実証事業のマネジメント、DADC・ABtCと連携したOuranos Ecosystemのアプリ要件(CFP算定・連携)の開発事業のリーダーを担当。その後、K&ESG社では、欧州電池規則におけるCFP・DD対応支援やCBAM対応に関するコンサルティングサービスを展開。CFPの算定経験は50商品以上に渡る(内、自動車・自動車部品関連は20商品)
また、TCFDレポート作成、CDP回答といったサステナビリティ情報開示の支援経験は60社超に上る